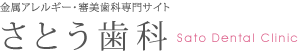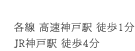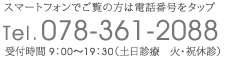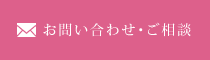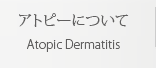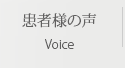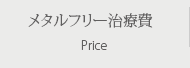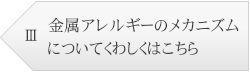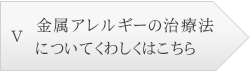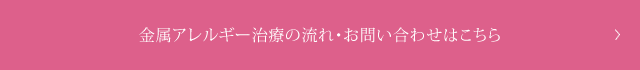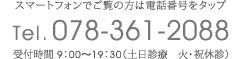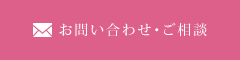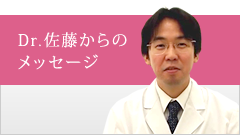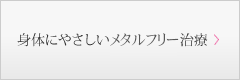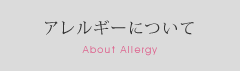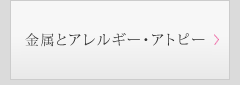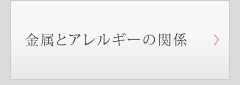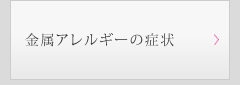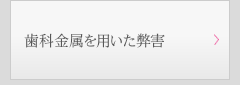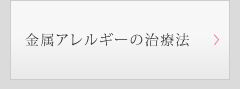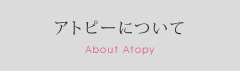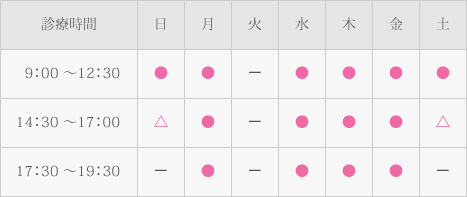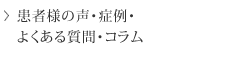- ホーム
- 歯科金属を用いた弊害
金属は口元の美しさを損なう原因に

銀歯やかぶせ物の土台など、歯科治療にはさまざまな金属が使用されています。その歴史は古く、紀元前からすでに使用されていたともいわれています。長い間に研究が進み、金合金や金銀パラジウム合金、コバルトクロム合金などが開発され、歯科治療において欠かせないものとされてきたのです。
しかし近年では口元の審美性を追求する傾向が強まり、歯科金属による審美面の悪化が問題視されるようになりました。
こちらではDr.佐藤が、金属を歯科修復治療に使用することによる障害についてご紹介します。
金属を用いた修復による金属アレルギー
金属アレルギーと皮膚疾患の関係性については、1970年代初頭から報告されていますが、歯科用金属との関係については注目されていませんでした。しかし、皮膚と同様に口腔内に歯科用金属を使えば、金属アレルギーを誘発する可能性は十分にあります。
特に口腔内は食べ物を咬み砕いたり、だ液を分泌したりするためとても過酷な環境です。そのような口腔内で使われることから、歯科用金属には生体親和性の高い材料が使われています。それでも金属アレルギーの反応があらわれることがあるため、そのような場合は、口腔内に加えて身体に触れる部分から原因になっている金属を排除するしかありません。
また、近年では異種金属が身体に触れることで電流が発生する「ガルバニック・アクション」も金属のイオン化を進める原因だといわれています。歯科金属の場合は長期間にわたって口腔内にあるため、さまざまな要因によって金属がイオン化して口腔内から身体に吸収されてしまいます。
そのため、もし金属アレルギーの反応が認められた場合、金属を一切使わないことがベストでしょう。しかし、ロングスパン(長い)のブリッジやパーシャルデンチャー(部分入れ歯)などは、どうしても金属を使用しなければいけません。そのような場合は、金属アレルギーが発生しにくいとされる純チタンを使用します。しかし、純チタンでも金属アレルギーが発症したという報告もあるので、歯科治療での素材選びは非常に重要です。
金属を用いた修復の問題点
歯科金属は、長年の間歯科修復治療に用いられてきました。しかし、経年によって以下のような問題を招くことがわかっています。
金属(メタル)の露出
以前には金属のつめ物・かぶせ物が多く使われてきましたが、近年では白い歯の中で金属が露出している状態であることに満足できない、天然歯と同等の機能性・審美性を望む患者さんが増えています。それは前歯だけでなく奥歯であっても同じであり、口を開けたときに見えるのが気になって、笑えなくなってしまうという方もいるほどです。
不自然な白色
かぶせ物の内側に金属(メタル)を使用する場合、金属色を隠すためにオペークというセラミック材料を用いる必要があります。これによって透明感が損なわれて色合いが単調になり、不自然な仕上がりになってしまいます。とくに前歯であれば、隣り合う歯との差がわかりやすくなり、不満が生じてしまうのです。
歯肉の変色
歯科金属は経年により、だ液によって溶け出してイオン化することで、歯ぐきに影響をして変色させてしまうことがわかっています。またかぶせ物の金属の土台(コア)を形成する際の削りカスが歯肉に食い込むことで、「metal tatoo」と呼ばれる変色を起こすこともあります。
歯質の変色
いわゆる「銀歯」といわれる金属のつめ物・かぶせ物には、従来アマルガムが使われていました。アマルガムは機能面では問題がない場合が多いですが、残存歯質に影響し、黒く変色させてしまうことがわかっています。
ブラックマージン
表面が白いセラミックのかぶせ物でも、内側のフレームが金属であったり、金属のコアを使用していたりすると、かぶせ物の適合不良や歯周病の進行などによって歯ぐきが退縮した場合に、内側の金属や変色した歯質が露出して黒いラインのように見えてしまうことがあります。これをブラックマージンといいます。

-
歯科金属を用いた治療には、以下のような問題点も生じます。
歯質削除量の増大 歯根破折(しこんはせつ) 金属のフレームの表面や前面をセラミックで覆う構造のクラウンでは、頬や舌に接する面の豊隆が大きくなりすぎないために、歯質を大きく削る必要が生じます。
これはMI(ミニマル・インターベンション:最小限の侵襲)の概念に反するものであり、患者さんの負担が大きくなってしまうといえます。
重度のむし歯で多くの歯質を削った際、かぶせ物を装着するために土台(コア)を構築します。この土台には従来金属が多く用いられてきました。しかし金属は、残歯を変色させるとともに歯質を弱くしてしまいます。
加えて金属は天然歯に比べて硬いことから、歯根破折を招く確率を高めてしまうのです。